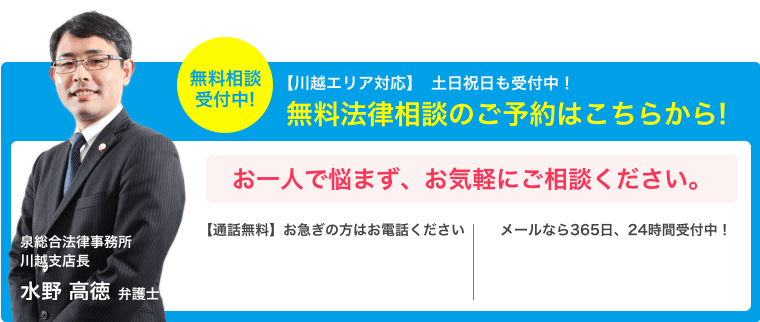個人再生手続における関係者への対応についての注意点

支払不能の恐れのある借金の一部だけを分割払いすれば、残る借金を原則としてすべて免除してもらえる個人再生手続では、様々な関係者への対応が必要になります。
このコラムでは、個人再生手続をする際に、手続に関わる人たちに対してどのような対応をすべきかを説明します。
1.個人再生手続の基本
(1) 手続の概要
借金全額を支払いきれない恐れのある債務者が、裁判所に再生計画の案を提出し、その計画に従った返済が履行可能であると認めてもらうことで、借金の支払負担を減らすことが出来る債務整理手続が、個人再生手続です。
再生計画に基づく返済は、借金総額のうち、後述の基準で定められた金額を、原則3年(最長5年)で債権者に支払うというものです。
最終的に、債務者が再生計画に従った返済を終えると、残っていた借金が免除されます。
(2) 手続の種類
個人再生手続には、手続の種類が二つあります。
①小規模個人再生
経済的メリットの大きい、一般的によく用いられる個人再生手続の種類です。
収入がさほど安定していなくても利用することができ、再生計画に基づく返済総額も少なくしやすいためです。
もっとも、債権者に反対され、個人再生手続そのものが失敗する恐れがあります。
②給与所得者等再生
債権者に反対されることなく借金の負担を軽減できる個人再生手続の種類です。
ただし、さほど利用されることはありません。
利用するには比較的高額で安定した収入が必要となるからです。
そのため、手続に反対することが予想される強硬な債権者がいるときに限り用いることになります。
(3) 最低限支払わなければならない金額の基準
再生計画に基づいて最低限支払わなければならない金額は、以下の基準額のうち、最も大きい金額です。
①最低弁済額
借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。
|
借金の額 |
最低弁済額 |
|---|---|
|
100万円未満 |
全額 |
|
100万円~500万円未満 |
100万円 |
|
500万円~1,500万円未満 |
借金の1/5の額(100万円~300万円) |
|
1,500万円~3,000万円未満 |
300万円 |
|
3,000万円~5,000万円 |
借金の1/10の額(300万円~500万円) |
②清算価値
清算価値とは、仮に債務者が自己破産をした場合に債権者に配当されると見込まれる金額です。
③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)
債務者の収入から税金などを引いたものの2年分です。
3つの基準の中で、最も高額となることが多いです。
(4) 個人再生委員
裁判所によっては、個人再生委員が手続を通して裁判所を補助することがあります。
個人再生委員は、債務者の借金や資産、家計の状況を調査して、裁判所に対し、債務者が再生計画に従った返済をすることが出来るかを報告します。
裁判所の中には、債務者に再生計画で予想される返済額を個人再生委員の指定口座に積立する「履行テスト」を行うところもあります。
(5) 債権者平等の原則
公の機関である裁判所を用いる個人再生手続では、債権者を平等に取り扱わなければなりません。
これを債権者平等の原則と呼びます。
債権者平等の原則から、個人再生手続で大きな問題となる点が二つあります。
一つが偏頗弁済です。
偏頗弁済とは、支払不能となった後に特定の債権者にだけ返済をすることです。
偏頗弁済があった場合、その金額が清算価値に上乗せされることになっています。
もう一つは、個人再生手続では、全ての債権者を対象としなければならず、特定の債権者を除外することが出来ないということです。
(6) 住宅資金特別条項
債権者平等の原則により全ての債権者を対象とせざるを得ない個人再生手続では、担保の付いている借金も整理対象となってしまうため、住宅ローン残高の残るマイホームなど、担保とされている財産は債権者により処分されてしまうことが原則です。
しかし、個人再生手続では、住宅資金特別条項(「住宅ローン特則」とも呼ばれます。)を再生計画に盛り込むことで、マイホームを処分されないようにすることが出来ます。
2.裁判所や個人再生委員
(1) 個人再生手続全般に対する協力
個人再生手続では、借金総額や家計状況の正確な把握が、制度の前提となっています。
また、清算価値が基準となっていますので、債務者の財産も明確に評価されなければなりません。
裁判所や個人再生委員は、上記の点について、債務者に必要な情報を提供するよう強く要求してきます。
下手にごまかそうとせず、真摯に協力してください。
一般の方ですと専門的な書類の理解は困難ですが、弁護士の協力により、段取りよく準備していきましょう。
(2) 現実的な再生計画の立案
再生計画が認可されなければ、個人再生手続による債務整理は始まりません。
そのためには、再生計画に基づく返済を実際に履行可能であるということを、返済額や収入、取り崩せる資産や、親族からの援助も含め、様々な経済力を総動員しつつ、決して背伸びせず、現実的な計画を立てる必要があります。
特に、個人再生委員は、債務者と面談するなどして具体的な調査を行うとともに、再生計画立案についても助言をしてくれます。
3.勤務先及び友人・親族など
(1) 借入をしている場合
債権者平等の原則があるため、個人再生手続から除外することは出来ません。
再生計画上の返済原資として重要な給与の確保、また、良好な人間関係の維持のためにも、事前に密な連絡を取っておきましょう。
なお、個人再生手続をする直前に一括返済していた場合には、偏頗弁済に当たりますので、その分清算価値に上乗せされてしまう恐れがあります。
(2) 勤務先からの借入を給与天引きで返済している場合
給与からの天引きによる返済は、偏頗弁済とされる恐れがあります。
すぐに勤務先に連絡して、天引きを止めてもらう必要があります。
(3)友人や親族に保証人になってもらっている場合
保証人が保証していた借金を手続から除外することは出来ません。
保証人へは借金残額の一括請求がされることになります。
ほとんどの場合、保証人にとって何らかの債務整理手続が必要になるほどの大きな経済的負担になるでしょう。
保証人への事前の連絡、相談、場合によっては弁護士を交えた協議を、絶対に行ってください。
4.一般の債権者
(1) 訴訟や差押えへの対応
弁護士に受任通知を送付された貸金業者は債務者へ取立てできなくなりますが、訴訟で財産を差押えることはできます。
もっとも、手続が始まれば、判決に基づく財産への差押手続は中止もしくは取消になります。
よほど強硬な業者でない限り、訴訟を提起してくることはありませんが、訴えられてしまった場合には、すぐに弁護士に連絡し、対応を依頼しましょう。
手続開始までに時間がかかってしまうと、さほど強硬で無い業者も訴訟を提起する恐れがあります。
迅速な準備を心掛けてください。
(2) ローンの残る自動車がある場合
自動車に関しては、住宅資金特別条項のような規定はありません。
そのため、自動車ローンが残っている場合には、個人再生手続をすると、自動車を債権者に引き上げられてしまうことがあります。
なお、自動車の引き上げを要求してきた債権者が、自動車販売店ではなく、信販会社の場合には慎重な対応が必要です。
なぜなら、自動車の車検証の名義や契約内容次第では、自動車の引き上げに応じたことが偏頗弁済とみなされ、自動車の時価が清算価値に上乗せされかねないからです。
この問題は、非常に難しい実務的な判断と対応が要求されます。
自動車ローンがある場合には、必ず、弁護士に詳細をお伝えください。
(3) 借金の有無や金額の決定
再生計画で返済すべき金額を定める基準となる借金の有無や金額について、手続の中で、債権者と争いになる可能性があります。
個人再生手続において、借金の有無や金額を手続上確定する債権調査手続というものがあります。
裁判所に対し、まず、債権者が届出を行い、債務者が債権者の届出に関する認否をします。
そして、債権者は、債務者の認否に異議を申し立て、裁判所や個人再生委員による債権評価の申立てをすることができます。
(4) 小規模個人再生での債権者の反対
手続の種類に関する説明でも触れましたが、小規模個人再生では、債権者が個人再生手続そのものに反対することが出来ます。
債権者総数の過半数が反対したとき、または、反対した債権者の持つ債権額が総額の過半数であるときは、再生計画が認可されず、手続は打ち切られてしまいます。
これを回避するには、債権者の動向をよく知る弁護士の助言の下で、債権者が反対できない給与所得者等再生を用いることになります。
5.住宅ローン債権者や住宅ローン保証会社
住宅資金特別条項を用いたとき、住宅ローンの残るマイホームを処分されずに済みますが、住宅ローンは一切減額されないことになります。
支払負担が再生計画に基づく返済と住宅ローンの二重負担となってしまうため、個人再生手続では、住宅ローンの返済スケジュールの変更が認められています。
手続上のスケジュール変更には、住宅ローン債権者や保証会社の同意は不要ですが、もし、それでも返済が困難ならば、住宅ローン債権者などとの協議で、住宅ローン減額や、より柔軟なスケジュール変更を行えるか協議する場合があります。
ただし、滅多に住宅ローン債権者は任意の交渉に応じないので、期待はしないでください。
6.借金問題でお困りの方は泉総合法律事務所へ
裁判所を利用する手続である個人再生手続では、裁判所やその補助者である個人再生委員への対応が最重要となるのはもちろんです。
それだけではなく、勤務先や友人親族から借金をしてしまっている場合には、身近な彼らも巻き込んでしまうことになります。
特に、保証人には大きな迷惑をかけかねません。
個人再生手続による債務整理を成功に導くためには、関係者に対して、専門家の助言に基づいた迅速な連絡や正確な調査・報告が不可欠なのです。
泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を個人再生手続で解決してきた豊富な実績があります。
借金問題でお困りの皆様のご相談をお待ちしております。
-
2019年12月19日債務整理 ゲームの廃課金による借金で破産をする場合は弁護士へ相談を
-
2020年5月8日債務整理 自己破産のデメリットには何がある?
-
2019年7月22日債務整理 主婦が家族(夫)に内緒で借金問題を解決する方法